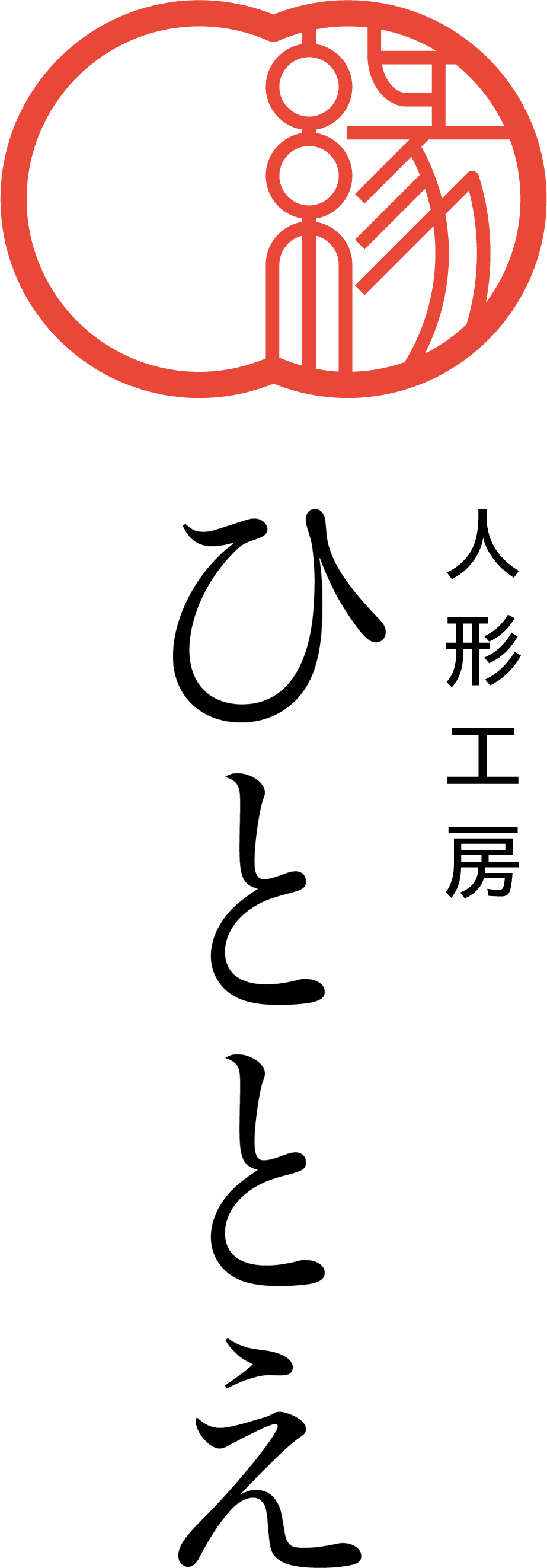ころんと丸く愛らしいお雛さま
木目込み人形のはじまりは江戸時代中期。
天然素材の桐塑製ボディに細い溝を彫り、布地を「木目込む」技法でつくるお雛様。
衣裳が型崩れしにくいため保管しやすく、丸く可愛らしいフォルムが近年人気を集めています。
※桐塑(とうそ)…桐の粉末に糊を混ぜて練った素材
天然素材の桐塑製ボディに細い溝を彫り、布地を「木目込む」技法でつくるお雛様。
衣裳が型崩れしにくいため保管しやすく、丸く可愛らしいフォルムが近年人気を集めています。
※桐塑(とうそ)…桐の粉末に糊を混ぜて練った素材
木目込み雛人形ができるまで
step.1
出来上がったときの衣裳の配色のバランスや、袖の重ねの幅などをイメージしながら、粘土でボディの原型を起こします。
起こした原型を木枠に入れて樹脂を流し込み「カマ」と言われる型を作ります。更にカマに桐塑を詰めて取り出す「ヌキ」の作業を繰り返します。
起こした原型を木枠に入れて樹脂を流し込み「カマ」と言われる型を作ります。更にカマに桐塑を詰めて取り出す「ヌキ」の作業を繰り返します。

step.2
ボディが抜けたら1週間ほど乾かし、表面のデコボコや余分な部分を丁寧に削っていきます。ひび割れなどは桐塑を足しながら竹べらで補修します。桐塑での制作は扱いも難しく手間がかかりますが、桐塑でしか出すことのできない曲線美や自然で温かみのある原型に仕上がります。

step.3
整えたボディ全体に「胡粉」を塗ります。これはボディの強度を上げるため、また、湿気で収縮するのを防ぐための大切な作です。衣裳を木目込む際にも、下地が白い方が綺麗な色目を出すことができます。
※胡粉(ごふん)…カキやはまぐりなどの貝殻を粉状にしたもの
※胡粉(ごふん)…カキやはまぐりなどの貝殻を粉状にしたもの

step.4
実際に布地を木目込むための筋を入れる「筋彫り」の工程に進みます。
2から3ミリ程の深さで、浅くても深くてもうまく木目込むことができないため、非常に高度な技術を要します。人形の仕上がりを左右する重要な工程です。
2から3ミリ程の深さで、浅くても深くてもうまく木目込むことができないため、非常に高度な技術を要します。人形の仕上がりを左右する重要な工程です。

step.5
筋彫りをした溝に、型紙に合わせて裁断をした布地を木目込ベラと糊を使ってしっかりと木目込んでいきます。手のひらサイズのひととえのお雛様の木目込みは非常に細かい作業で着せつけた衣裳にしわが寄らないよう布地を逃がしながら、細心の注意を払います。

step.6
頭師(かしらし)によってつくられた頭や手をボディに取り
つけていきます。
角度や向きに注意しながらお顔をつけ、髪の毛をブラシで整えます。全体の仕上がりを確認したら、ようやくお雛様の完成です。
角度や向きに注意しながらお顔をつけ、髪の毛をブラシで整えます。全体の仕上がりを確認したら、ようやくお雛様の完成です。

ひととえの木目込雛人形
ころんと丸いフォルムが愛らしく現代の住宅にぴったりの木目込み人形。
年月が経っても型崩れの心配がないのも魅力です。
ひととえの原型師が丹精込めて制作したオリジナル原型のボディに 最高級の美しい絹織物を木目込みます。小さな宝石のようなお雛様をお届けいたします。
ひととえの原型師が丹精込めて制作したオリジナル原型のボディに 最高級の美しい絹織物を木目込みます。小さな宝石のようなお雛様をお届けいたします。
インテリアにすっと馴染む木目込み人形

木目込み人形の魅力はなんといっても愛らしいまあるいフォルムです。
アートとしてもインテリアにすっと馴染むほど、デザイン性の高い雛人形です。
合わせる背景やお道具によって、スタイリッシュな雰囲気にも古典的な雰囲気でもお飾り頂けます。
瞳がかがやく『入れ目』仕上げの上品で愛らしいお顔

ひととえのお雛様は、愛らしさと上品さを調和させたお顔が自慢です。
ふっくらまるい輪郭と、黒目がちなつぶらな瞳がチャームポイント。入れ目仕上げのガラスの瞳が表情に命を吹き込んでいます。
木目込み雛人形では、サイズごとに選べるお顔が異なります。
木目込み雛人形では、サイズごとに選べるお顔が異なります。
安心のお人形10年保証

うっかりお人形を落としてしまった!そんな時にも安心です。木目込み人形は納品日より10年間修理費無料でお直しさせていただきます。(衣裳着人形は1年間)
アフターフォローもしっかりとご対応させて頂いておりますので、ご不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。